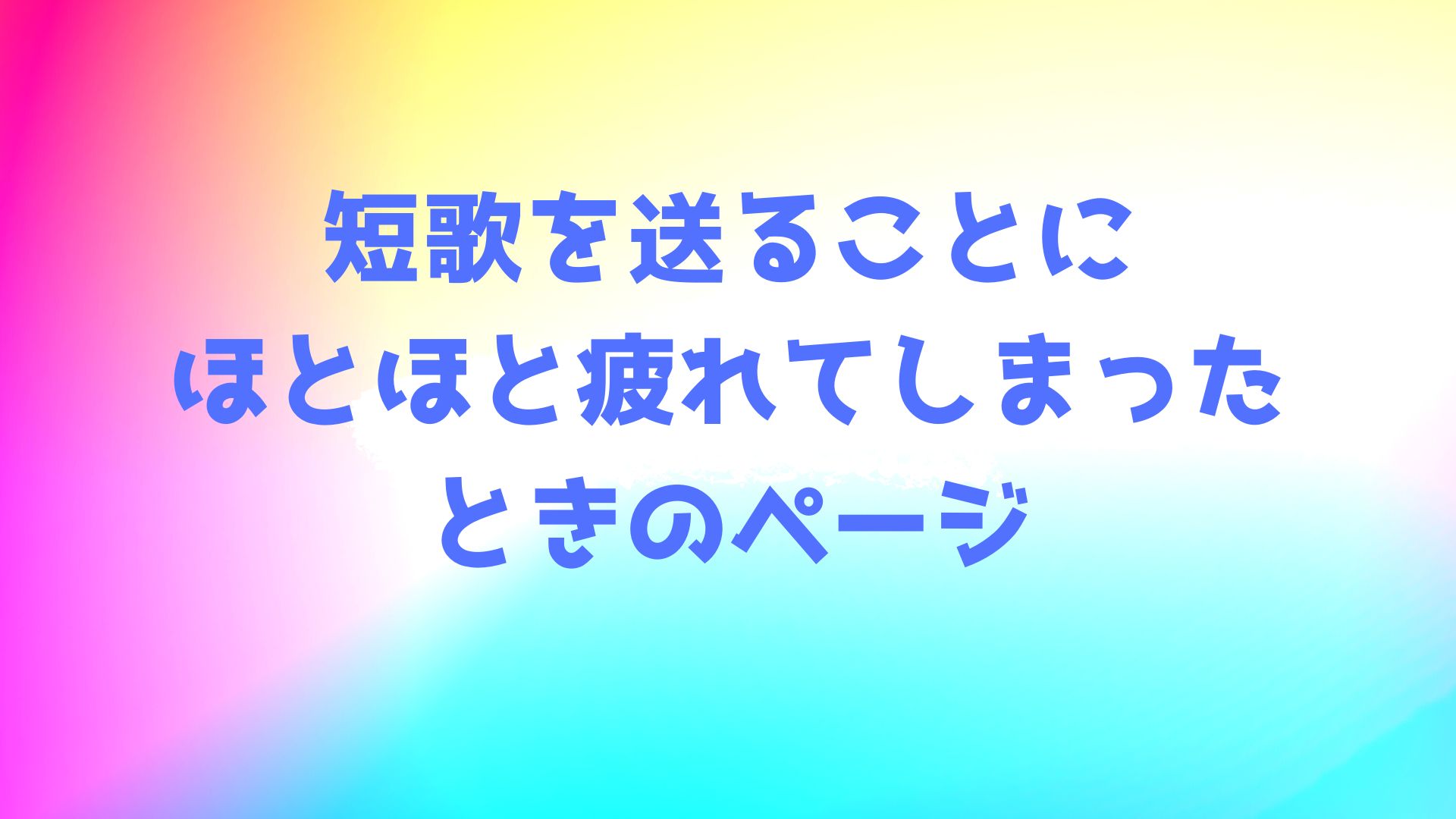目 次
末梢的である

ものうげに頭めぐらすはだら牛瞳の中に夕日は燃えつ(知らない人)
角川書店
『短歌を作るこころ』
佐藤佐太郎
「作歌上の注意」より
佐藤佐太郎の著書より引いた一首である。
「おちいりやすい欠点」の例として、佐藤佐太郎は、この一首を挙げておられる。
ご自身でわざと「欠点」をのこして作歌なさったのか、「欠点」の一例に、どなたかの投稿歌からこれを挙げたのか。
物の真実、中心を見ないで、どうでもいいような点に興味を持っている。第二義的な見方、感じ方。「甘い」のも末梢的である。
同書・同章
(内容(見方・感じ方))より
同じ「牛」でも斎藤茂吉ならこう詠む
わたつみに向ひてゐたる乳牛が前脚折りてひざまづく見ゆ(斎藤茂吉)
佐藤佐太郎は、『短歌を作るこころ』の(作歌の楽しさ)において、この一首を引いた。
房州の浜で見た情景で、渚につながれて立っていた牛がいま、ひざを折ってうずくまったところである。すこしも難しいところがなく、安らかに見たままをいっている。
同書・「短歌を作るこころ」(作歌の楽しさ)より
(中略)
見たままを飾らずに確かにいうのが短歌表現の初歩であると同時に究極でもある。
海を見て前脚を折る牛だぜ
声を出さなくなるよね
でも、この一首が、「見たままを飾らずに確か」なる短歌であることは、その通りではないかと
「瞳の中に夕日」ではやはりよくないようだ
ものうげに頭めぐらすはだら牛瞳の中に夕日は燃えつ(知らない人)
たしかにこのような牛はいよう。
ちゃんとイメージできるし、ここの、それこそ「ものうげ」なトーンも、ここに、「夕日」なる色彩があることも悪くはない。
でも、一言、つまんない。
牛を勝手にものうげにしていないか
そも瞳に夕日はまことにあったのか
なるほど第二義的とはよく言ったものだ
それを想定していたかいないか
(知らない人)には持てない驚きを(斎藤茂吉)は歌にしてしまえるわけだ
ものうげに頭めぐらすはだら牛瞳の中に夕日は燃えつ(知らない人)
わたつみに向ひてゐたる乳牛が前脚折りてひざまづく見ゆ(斎藤茂吉)
うその話ではない
目に浮かぶ
が、驚けない
アタリマエだ
本人が「あっ」ってなって作っていない
ますます佐藤佐太郎の言っている通りだ。すなわち第二義的。
うその話ではない
目に浮かぶ
そして、身を乗り出してしまう
アタリマエだ
本人が「あっ」ってなって作っている
モチベーション=次はできるかできないか
短歌のモチベーションがなくなってきた、とする。
創作意欲だとか何だとか、まあそういうことなのであろうが、要は、何かを創作してみたい、との意欲があっても、出来上がったものは、いつまでたっても未熟なことに落胆しかないからであろう。
第二義的なことでは、いくらせっせと作っても、いずれはもういいや、ともなろうか。それではいつまでも創作意欲など持てるわけがない。
陳腐なイメージと色彩では、いくら体裁のいい仕上がりの歌ができても、読後、つまんないに決まっているではないか。
まず何を見た
何に驚いた
わたつみに向ひてゐたる乳牛が前脚折りてひざまづく見ゆ(斎藤茂吉)
わちゃ~
自作の未熟なことにいくら落胆しても、たとえば茂吉の「牛」のようなものができるまでは、と肚を括ってしまうのはどうか。
できない、
なんて言わないで。
何度でも、
何度でも徒労を繰り返して。
リンク
『斎藤茂吉の短歌研究』は、斎藤茂吉の作品を、一首ずつ解説してあります。斎藤茂吉について、短歌作品以外にも記事が豊富にある、至れり尽くせりのサイトです。